学期末の発表、グループワークでの報告、課題研究の発表など、学校生活には「人前で話す機会」が意外とたくさんあります。うまくプレゼンできたら自信につながるし、聞き手にも伝わりやすくて結果も良くなります。ここでは、発表の成功率を高めるための具体的な「コツ」を、わかりやすく紹介します。
ぜひ、次の発表に活かしてください。
今回は、学校での発表が上手くなる!プレゼンテーション上達のコツを特集します。

プレゼンテーションが上達して見えるコツを教えて欲しいなぁ!
- 慣れるまでは原稿を必ず使い、練習をとことんする。ぶっつけ本番でうまくいくのは場数を積んだ人だけ。
- パワーポイントなどでスライドを作る場合、1スライド1テーマにする。文字の多いスライドは見られない。
- プレゼンは“プレゼント”。聞いてくれている人に対して目を配り、反応を見ながら話せるようになれば一皮剥けたプレゼンができる。
1.原稿&練習を徹底せよ
発表の段階で練習が足りないと、「頭が真っ白」「何を言おうとしていたか忘れた」というアクシデントが起きることがあります。特に学校の発表では時間も限られていますし、聞き手(先生・クラスメイト)に「何を伝えたいか」が明確に届くことが大切です。ここで、まず理解しておきたいのが:
- 「慣れるまでは原稿を必ず使う」ということ。手元に発表の流れを書いた原稿を用意し、自分の言葉で読めるようにしておきましょう。
- 「練習をとことんする」こと。声に出して読んで、発表の時間を計って、鏡やスマホで自分の姿をチェックしてみてください。
- ぶっつけ本番でうまくいくのは、場数を積んだ人だけと心得ましょう。初めての発表や緊張する場では、準備がカギです。
具体的には、次の流れがおすすめです。
- 発表内容を構成し、原稿案を書く。導入→本論→結論という順序を基本に。
- 原稿をもとに声に出して読む。一回目は時間を測らず、二回目以降は“制限時間内”に収まるかチェック。
- 発表する場を想定して、鏡を見ながら/スマホで録画して自分のジェスチャー・話すスピード・目線を確認。
- 内容や言い回しで気になるところがあれば修正し、再度読み直し。できれば発表直前にも少し目を通す。
このように練習を重ねれば、「何を話すか」が頭に入ってくるので、多少のハプニング(プロジェクターのトラブル、マイク無し、教室の騒音など)にも柔軟に対応できます。逆に、原稿も練習も無しで当日を迎えると、聞き手の信頼を得にくく、内容もぼやける可能性が高まります。
2.スライドを使うなら“1スライド1テーマ”を守る
近年、多くの学級・授業で Microsoft PowerPoint や Google スライド を使った発表が当たり前になっています。スライドを使うことで視覚的な補助ができ、発表内容が伝わりやすくなる反面、逆にスライドが“文字でぎっしり”になってしまうと危険です。
ここで守ってほしい大原則が:
「1スライド1テーマ」です。
- スライドあたりに複数の異なるテーマ(例:原因・対策・予算など)を詰め込むと、見る側が混乱します。
- 文字が多すぎるスライドは、聞き手がスライドを読んでしまって“あなたの話”を聞かなくなります。つまり、あなたの発表が“無音の読み上げ”になりがちです。
- スライドは“補助資料”。メインは「あなたが話す内容」。だから、シンプルかつ視覚的に伝わる作りが望ましいです。
スライド作成の際、意識すべきポイント:
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| スライド枚数 | 発表時間が5分なら、枚数は7〜10枚くらいが目安 |
| 文字量 | 一行に5〜7語、1スライドに3〜4行程度を目安に |
| フォント・色使い | 読みやすさ重視(背景と文字色のコントラストを確保) |
| 視覚素材 | グラフ・写真・アイコンは使えるなら活用して、視線を誘う |
例えば、「発表の目的」というテーマなら、スライド一枚に「発表の目的:○○を明らかにする」「背景:□□」などを二分割せず、一枚でひとつのメッセージに絞り、発表者としてその背景や補足を口頭で説明する方が効果的です。
3.“聞き手”に目を配る。プレゼンは“プレゼント”だ。
発表で良くある失敗のひとつに、「ただスライドを読み上げて終わる」というものがあります。話している側は“内容を伝えよう”として精一杯ですが、聞き手にとっては「聞く側の気持ち」が置き去りになってしまうこともあります。ここで大切なのが:
「プレゼンは“プレゼント”」という意識です。つまり、聞いてくれている人に価値(=分かりやすさ・興味・納得)を届けるという気持ちを持つことです。
具体的には:
- 話している時、クラスメイトや先生の方を“適宜”見て、反応を確認。目を配ることで、興味が失われていないか、置いてきぼりになっていないかを察知できます。
- 聞き手がうなずいたり、首をかしげたりしていたら、少し立ち止まって「この点、もう少し説明しますね」とフォローできる余裕を持ちましょう。
- 声のトーン・スピード・間(ま)を意識。早口だと聞き手が追いつきません。逆にゆっくりすぎると眠くなります。「少しゆっくり目」くらいがちょうどいいです。
- ジェスチャーや表情を使って、聞き手を引き込みましょう。無表情・棒読みは避けたいところです。
このように“聞き手を主体にした発表”ができる人は、内容が同じでも印象がぐっと良くなります。実際、先生やクラスメイトの反応も「話し手を見ている/聴衆に配慮している」と感じると、興味を持たれやすくなるという声も少なくありません。
まとめ:実践してレベルアップしよう
ここまで、学校での発表が上手くなるための3つの大切なコツを挙げました:
- 原稿を作って、練習を徹底する。ぶっつけ本番でうまくいくのは場数を積んだ人だけ。
- スライドを使う場合は「1スライド1テーマ」、文字の多いスライドは見られないという認識を持つ。
- 発表は“プレゼント”。聞いてくれている人に目を配り、反応を見ながら話すことで、一皮剥けたプレゼンができる。
これらを意識して、次の発表に向けて準備を進めてみてください。例えば、発表のテーマを決めたら、まず原稿をざっと書き、スライド案を出し、声に出して通してみる。友だちや家族に聞いてもらってフィードバックをもらうのもおすすめです。
練習を重ねるごとに、「あ、これなら大丈夫だ」と思える瞬間が必ず来ます。そして、その安心感が「聞き手にも伝わる自信」につながります。準備をして「今日はいい発表だったね」と言われることを目指して、ぜひ挑戦してください。応援しています!

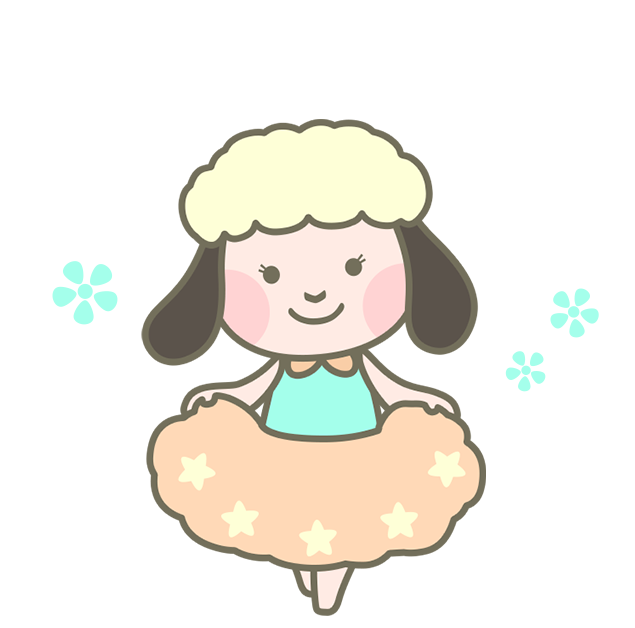
プレゼンや発表って人前で話さなくちゃいけないし、とっても緊張するなぁ
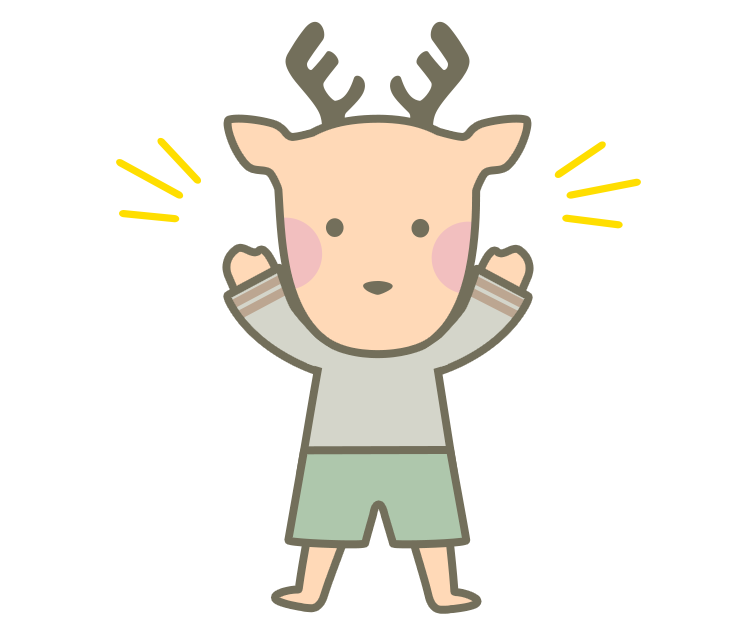
ちょっとしたコツを押さえるだけで、他の人より一歩抜きん出た発表ができるようになるよ!

この記事を読んでいる人には、こちらの記事もおすすめです!




YouTubeでも情報発信をしています