
志望校って、いつまでに決めればいいんだろう…
受験を控えるお子さんを持つ保護者の方、そして受験生本人にとって、これは避けては通れない、非常に重いテーマではないでしょうか。
志望校を早く決めた方が良いとは分かっていても、
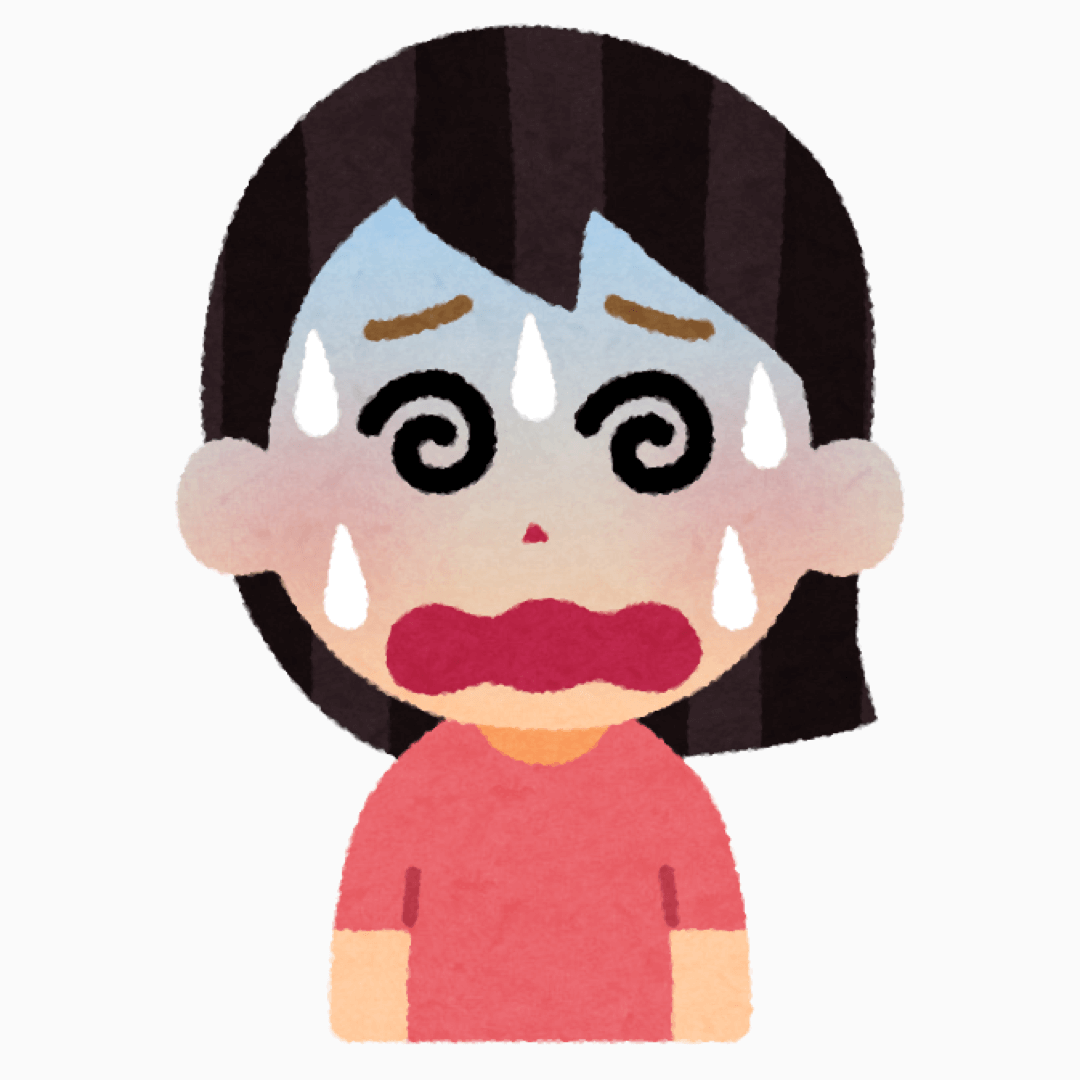
「子どもの成績ではまだ考えられない」
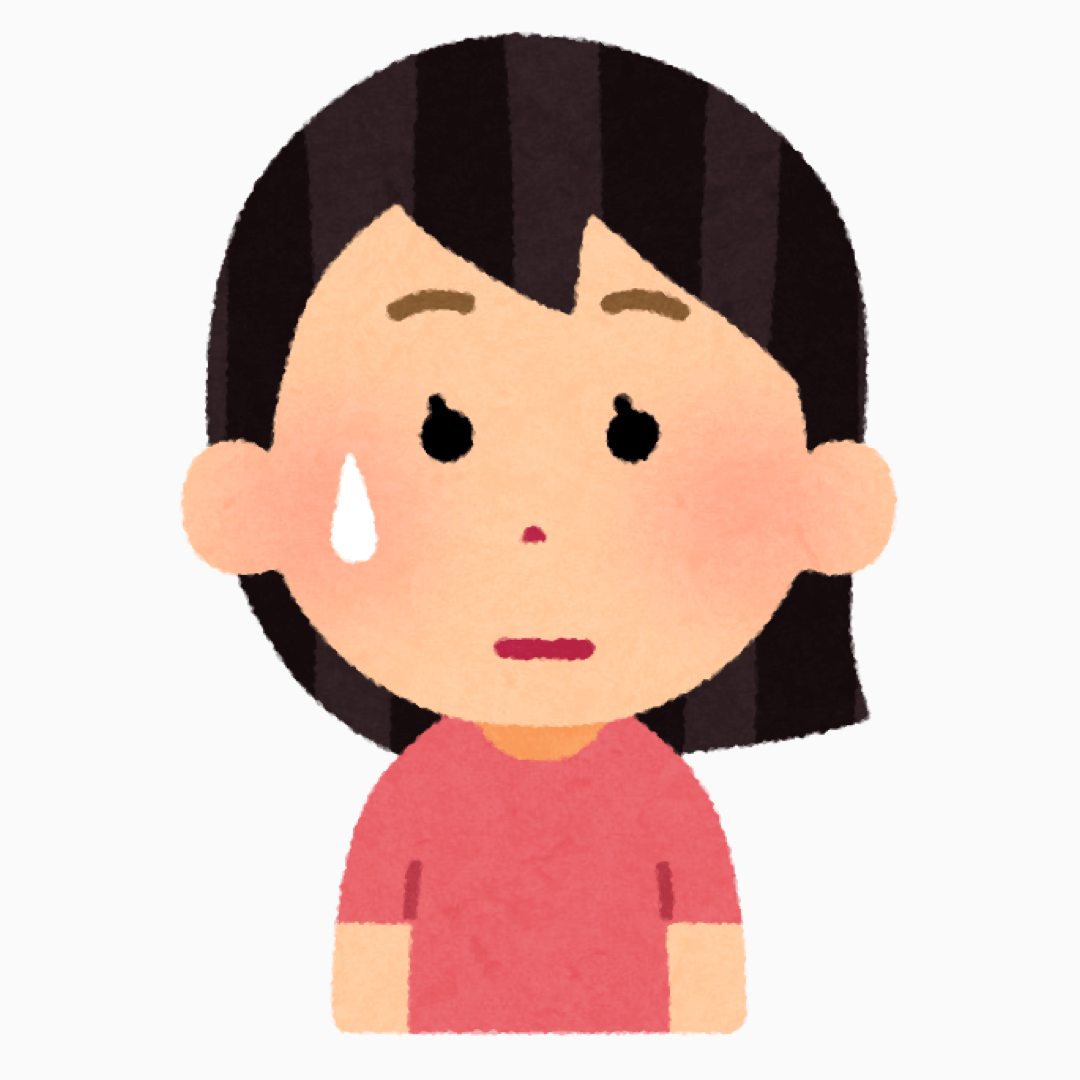
「本人がどこに行きたいのか分からない」
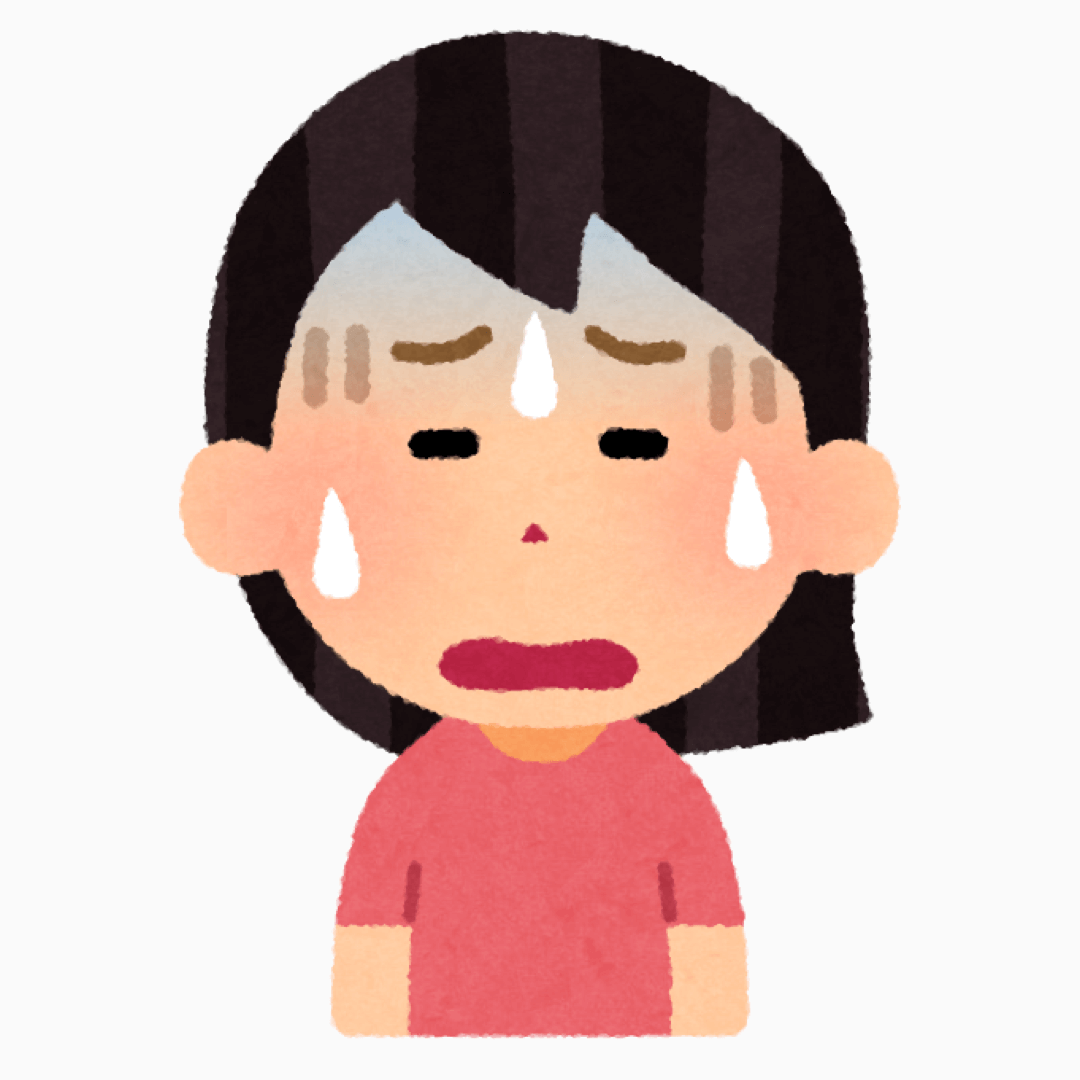
「もっと良い学校があるかもしれない」
といった理由で、決断を先延ばしにしてしまうケースは少なくありません。
しかし、志望校決定のタイミングは、受験の成否を大きく左右すると言っても過言ではないのです。
早く決めることで、目標に向かって一直線に勉強でき、無駄な努力を避けられます。一方で、決断が遅れると、対策が後手に回り、精神的な焦りが生まれ、結果的に「もっと早く決めておけばよかった…」という後悔につながることもあります。
この記事では、長年多くの受験生を見てきた経験から、中学受験・高校受験・大学受験それぞれにおける志望校決定の具体的なタイムリミットと、その根拠を詳しく解説します。
さらに、後悔しない志望校を選ぶための具体的な5つのステップ、どうしても決められない時の対処法、そしてお子さんをサポートする保護者の適切な関わり方まで、網羅的にご紹介します。
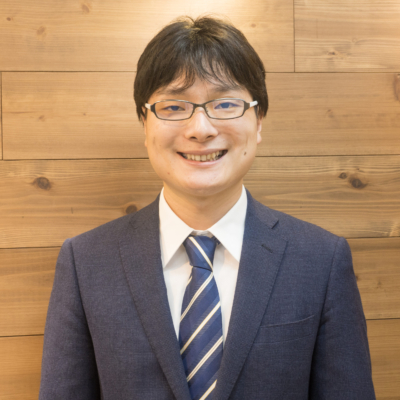
この記事を読み終える頃には、「いつまでに、何をすべきか」が明確になり、自信を持って志望校選びの第一歩を踏み出せるはずです。

第1章:なぜ志望校を早く決めるべきなのか?受験を有利に進める5つの理由
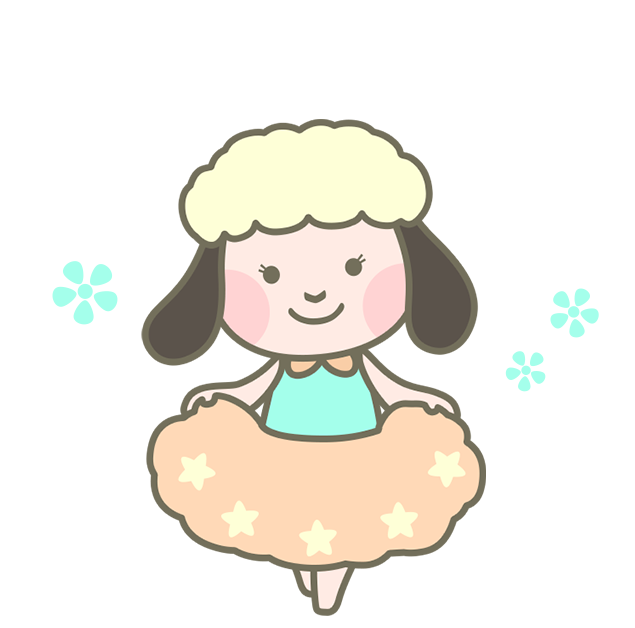
ギリギリまで可能性を探りたい…
という気持ちも分かりますが、志望校の早期決定には、それを上回る大きなメリットがあります。なぜ「できるだけ早く決めた方が有利」なのか、その理由を5つの観点から具体的に見ていきましょう。
学習計画の精度が上がり、無駄な勉強がなくなる
最大のメリットは、学習の「選択と集中」が可能になることです。学校によって、入試科目、配点、出題範囲、そして問題の傾向は全く異なります。
- 中学受験: 学校ごとに国語の記述問題の多さや、算数の図形問題の難易度などに大きな差があります。特に公立の中間一貫校で行われる適性検査と、私立校である入学試験では出題形式が全く異なります。さらに、小学生で習う学習内容とは全く異なるので、どこに注力するかは大きな差につながることがあります。
- 高校受験: 公立高校では内申点が重要視されますが、私立高校では当日の学力試験の比重が高いなど、対策の軸足が変わります。また、特定の教科に比重が置かれている場合もあります。
- 大学受験: 共通テストと二次試験の配点比率、二次試験の科目(例えば、同じ理系でも物理・化学指定か、生物も選択可能か)など、志望校次第でやるべきことが劇的に変化します。国公立を狙うのかと私立一本でいくのかでは対策すべき問題量が全く違います。
志望校が決まっていれば、その学校の入試傾向に特化した対策を早期から始められます。これは、闇雲に全範囲を勉強するライバルに対して、計り知れないアドバンテージとなります。
「絶対に合格する」という強いモチベーションが生まれる
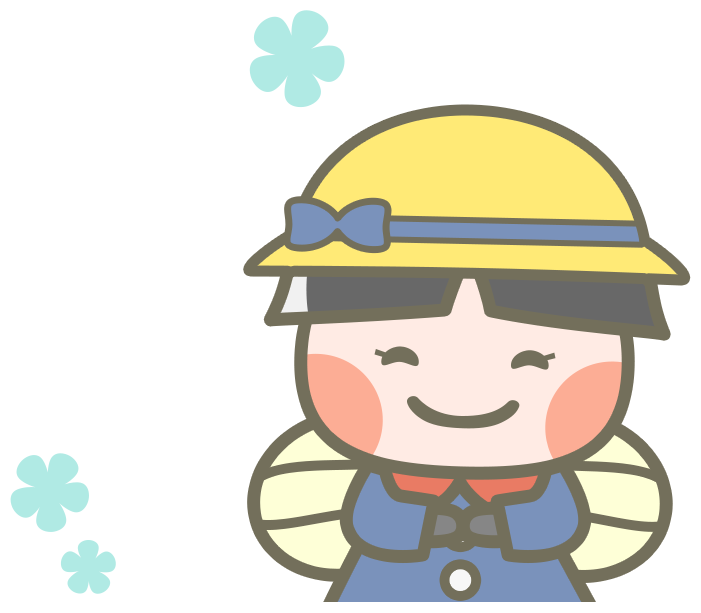
△△高校の文化祭に行きたい
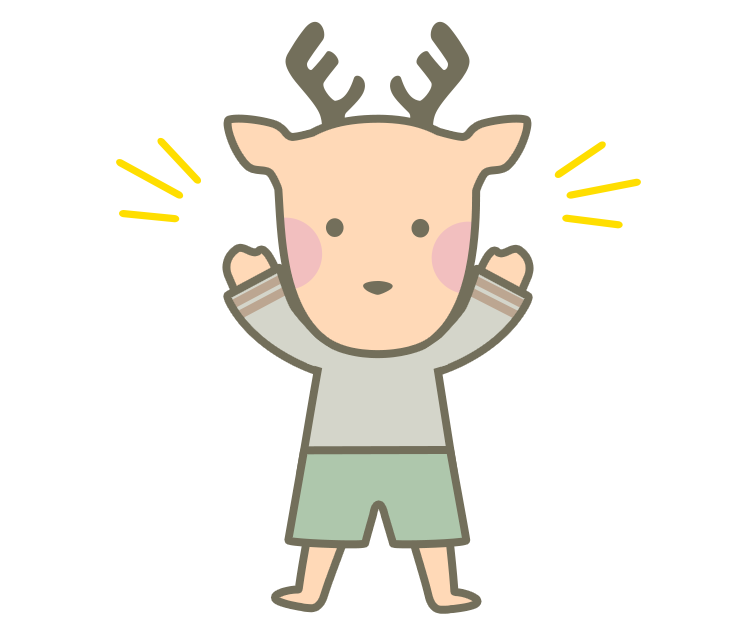
〇〇中学校の制服を着たい

□□大学のキャンパスで学びたい
具体的で鮮明な目標は、日々の辛い勉強を乗り越えるための最も強力なガソリンになります。成績が伸び悩んだ時や、やる気が出ない時に、「あの学校に行きたいから頑張るんだ」という強い気持ちが、自分を再び机に向かわせてくれるのです。
必要な情報を早期から効率的に収集できる
志望校が決まれば、集めるべき情報も明確になります。 オープンキャンパスや学校説明会の日程はもちろんのこと、過去問の入手、在校生や卒業生の口コミ、塾で開催される志望校別特訓の情報など、アンテナを張るべき対象が絞られます。情報戦とも言われる受験において、早くから的を絞って情報を集められることは、大きな強みです。
精神的な余裕が生まれ、勉強に集中できる環境が整う
「どこを目指せばいいんだろう…」という迷いは、知らず知らずのうちに大きなストレスとなります。目標が定まらない状態では、勉強していても「このやり方で合っているのか?」という不安が常につきまといます。 早くに志望校という軸を定めることで、進路への迷いがなくなり、目の前の勉強に100%集中できる精神的な安定を得ることができます。
併願校戦略をじっくり練る時間が確保できる
特に中学受験や大学受験では、第一志望校だけでなく、実力相応校(第二志望)、安全校(滑り止め)を組み合わせた「併願戦略」が極めて重要です。 第一志望が早く決まっていれば、その学校との入試日程のバランス、入試問題の傾向の相性などを考慮しながら、最適な併願校をじっくりと時間をかけて検討することができます。
第2章:後悔しない志望校の決め方【5つのステップ】
では、具体的にどうやって志望校を選んでいけばよいのでしょうか。偏差値だけで決めて後悔しないために、以下の5つのステップを踏むことをお勧めします。
ステップ1:自己分析「自分(我が子)は何をしたいのか?」を知る
まず、偏差値という物差しを一旦脇に置き、自分(お子さん)の内面と向き合います。
- 好きなこと・得意なこと・苦手なこと: 何をしている時が楽しいか?どんな科目が得意か?
- 将来の夢や興味のある分野: (具体的でなくてもOK)どんな大人になりたいか?何に興味があるか?
- 学校に求める条件: 校風(自由か、規律正しいか)、通学時間、部活動、制服の有無、施設の充実度、学費など、譲れない条件をリストアップします。
この自己分析が、学校選びの「ブレない軸」となります。
ステップ2:情報収集「選択肢を広く集める」
自己分析で出てきたキーワードをもとに、候補となる学校の情報を幅広く集めます。
- インターネット: 学校公式サイトは必須。その他、口コミサイト、SNS(InstagramやXで学校名を検索すると、在校生のリアルな声が見えることもあります)も参考に。
- 資料請求: パンフレットや募集要項を取り寄せ、教育理念やカリキュラム、進学実績などをじっくり読み込みます。
- 塾や学校の先生: 多くの生徒を見てきた専門家からの客観的な情報は非常に貴重です。
ステップ3:体験「五感で学校の魅力を感じる」

集めた情報が本当かどうかを確かめるために、必ず現地に足を運びましょう。
- オープンキャンパス・学校説明会:
- 見るべきポイント:
- 生徒の表情: 楽しそうか、挨拶はしてくれるか。
- 先生の熱意: 生徒への接し方、説明の分かりやすさ。
- 施設: 教室、図書館、トイレなど、清潔で使いやすそうか。
- 通学路と周辺環境: 駅から安全に通えるか、寄り道するような誘惑が多すぎないか。
- 見るべきポイント:
- 文化祭・体育祭: 最も学校の「素顔」が見えるイベントです。生徒が主体的に楽しんでいるか、学校全体の雰囲気はどうかを肌で感じましょう。
パンフレットでは魅力的に見えても、「実際に訪れたら、なんだか合わない気がした」ということは頻繁にあります。その逆もまた然りです。
ステップ4:実力測定「現在地を客観的に把握する」
学校の魅力と同時に、自分の学力という現実も直視する必要があります。
ここで活躍するのが模擬試験(模試)です。 模試によって、現時点での学力と、志望校合格に必要な学力との「距離」が客観的な数値(偏差値や合格可能性判定)で分かります。この結果は、挑戦校、実力相応校、安全校を判断する上で不可欠なデータとなります。
ステップ5:絞り込みと決定「優先順位をつけて決断する」
ステップ1~4で集めた情報を全て並べ、ステップ1で定めた「軸」に照らし合わせながら、優先順位をつけて候補を絞り込んでいきます。 この段階では、必ず本人、保護者、そして可能であれば塾や学校の先生を交えて、三者で話し合うことが重要です。それぞれの視点から意見を出し合うことで、より納得感のある決断ができます。
第3章:【中学受験】志望校決定のタイムリミットは「小学5年生の冬」

中学受験における志望校決定の大きな節目は、小学5年生の冬休み前後です。
なぜ「小5の冬」なのか?
- 小6からの志望校別対策に間に合わせるため: 多くの進学塾では、小学6年生になると「〇〇中コース」といった志望校別の特訓授業が始まります。このコース分けに間に合うように、ある程度志望校を固めておく必要があります。
- 学習内容の深化: 小学校の学習範囲を終え、より難易度の高い応用問題に取り組む小6の時期。目標が定まっているかどうかで、学習の密度が大きく変わります。
- 模試の判定が現実味を帯びる: 小4や小5前半の模試は、まだ受験者層も固まっておらず、判定も甘めに出がちです。小5の秋以降になると、受験本番に近い母集団での成績が出るため、より現実的な志望校選定が可能になります。
中学受験の志望校決定スケジュール例
- 小4: 様々な学校に興味を持つ時期。親子で文化祭や説明会に足を運び、「中学校ってこんなところなんだ」というイメージを膨らませます。
- 小5(夏): 気になる学校のオープンキャンパスに参加。塾の夏期講習や模試を通じて、自分の学力レベルを把握し始めます。
- 小5(冬): 第一志望校を仮決定。 偏差値だけでなく、校風や教育方針を重視して選びます。同時に、併願する可能性のある学校を複数リストアップします。
- 小6(夏): 過去問演習を開始。第一志望との相性を見ながら、併願パターン(挑戦校・相応校・安全校)を具体的に固めていきます。
- 小6(秋以降): 模試の最終結果などを踏まえ、出願校を最終決定します。
中学受験ならではの注意点
中学受験は、本人の意思以上に親の役割が非常に大きいのが特徴です。情報収集、スケジュール管理、そして何より子どもの精神的な支えとなることが求められます。ただし、親の希望を押し付けすぎず、あくまで主役は子どもであるという姿勢を忘れないことが、後悔しない結果につながります。
第4章:【高校受験】志望校決定のタイムリミットは「中学3年生の夏休み」

高校受験では、中学3年生の夏休み中、遅くとも夏休み明けまでに志望校を確定させるのが理想です。
なぜ「中3の夏」なのか?
- 内申点(調査書点)が重要だから: 多くの公立高校入試では、中学3年生の成績(特に2学期)が内申点として大きく影響します。「この高校に行くには、次の定期テストで〇点以上取る必要がある」という明確な目標を持つことで、内申点対策のモチベーションが格段に上がります。
- 夏休みが学力向上の天王山だから: 夏休みは、総復習と苦手克服に集中できる最後のまとまった期間です。志望校が決まっていれば、その学校のレベルに合わせて「夏休みに何をすべきか」という具体的な学習計画を立てることができます。
- 秋からの三者面談に備えるため: 2学期には、担任の先生との三者面談で具体的な受験校を決定していきます。夏休みまでに志望校を決めておくことで、先生に相談しやすくなり、的確なアドバイスをもらえます。
高校受験の志望校決定スケジュール例
- 中1・中2: まずは日々の授業と定期テストを大切にし、内申点を意識した学校生活を送ります。気になる高校があれば、文化祭などに気軽に参加してみましょう。
- 中3(春~夏): 部活動の引退も視野に入る時期。本格的に受験生としての意識を持ち、オープンキャンパスには必ず参加します。模試の結果や内申点を踏まえ、夏休み中に第一志望校と併願する私立高校を決定します。
- 中3(秋): 三者面談で最終的な意思確認。模試の結果を見ながら、必要であれば志望校のレベル調整を行います。
- 中3(冬): 出願手続き。あとはひたすら過去問演習と苦手解決に集中し、最後の追い込みをかけます。
高校受験ならではの注意点

高校受験では、公立高校と私立高校の組み合わせが戦略の鍵となります。
第一志望の公立高校に挑戦しつつ、内申点を活かせる「併願優遇」制度のある私立高校や、確実に合格できる「滑り止め」の私立高校を組み合わせて受験プランを立てることが一般的です。
第5章:【大学受験】志望校決定のタイムリミットは「高校2年生の冬~高校3年生の春」
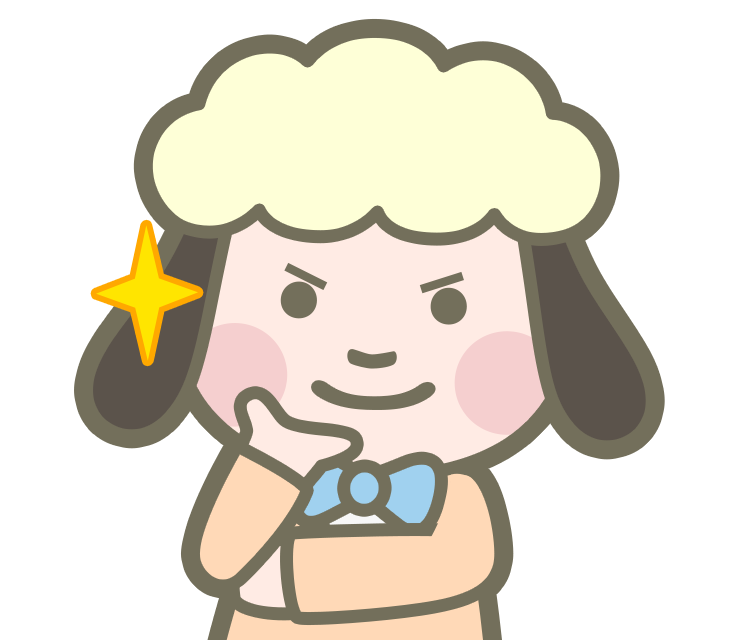
大学受験の場合、高校2年生の冬から高校3年生に進級する春までに、志望校(少なくとも志望大学群と学部系統)を決めることが望ましいです。
なぜ「高2の冬~高3の春」なのか?
- 受験科目を確定させるため: 大学入試は、選択科目が非常に複雑です。特に理科(物理・化学・生物)や社会(日本史・世界史・地理・公民)は、志望校によって必要な科目が異なります。高3からの演習量を確保するためにも、高2のうちに受験科目を確定させる必要があります。
- 共通テストと二次試験の対策バランスを決めるため: 国公立大学を目指す場合、共通テストと二次試験(個別学力検査)の両方の対策が必要です。大学によってその配点比率は大きく異なるため、志望校を決めないと、どちらに重点を置くべきかという戦略が立てられません。
- 推薦入試(総合型選抜・学校推薦型選抜)の準備: これらの入試形態を検討する場合、評定平均の確保や課外活動の実績、志望理由書の作成など、早期からの準備が不可欠です。高3の春には、推薦を利用するかどうかの判断が必要になります。
大学受験の志望校決定スケジュール例
- 高1: まずは文理選択が最初の大きな分岐点。オープンキャンパスに積極的に参加し、学問への興味や大学の雰囲気を知ります。
- 高2(夏~秋): 多くの生徒が本格的な受験勉強をスタートさせる時期。大学名だけでなく、学部・学科レベルで興味のある分野を絞り込んでいきます。
- 高2(冬)~高3(春): 第一志望の大学・学部を決定。 受験に必要な科目を確定させ、年間の学習計画を立てます。
- 高3(夏): これまでの模試の結果を踏まえ、挑戦校・実力相応校・安全校からなる併願校リストを作成します。
- 高3(秋以降): 過去問演習を本格化。共通テストの結果次第で出願先を変更する可能性も視野に入れつつ、出願校を最終決定します。
大学受験ならではの注意点
大学受験は、その後の人生に直結する専門分野を決める重要な選択です。「大学のネームバリュー」だけで選ぶのではなく、「その大学のその学部で、何を4年間かけて学びたいのか」を徹底的に考えることが、後悔しない選択につながります。
また、万が一の結果に備え、「浪人するのか、合格した大学に進学するのか」を事前に家族で話し合っておくことも大切です。
第6章:どうしても志望校が決まらない…そんな時のための4つの処方箋
これまで早期決定の重要性を説いてきましたが、「そうは言っても決められない」という方も多いでしょう。そんな時に試してほしい、4つの対処法をご紹介します。
1. 「仮の志望校」を決めてみる
完璧な一校でなくても構いません。現時点で「一番良いな」と思う学校を「仮の目標」に設定しましょう。
目標が一つあるだけで、勉強のモチベーションや計画の立てやすさが格段に変わります。勉強を進める中で、新しい目標が見つかれば、その時に見直せば良いのです。
2. 消去法で考える
「行きたい学校」が思いつかないなら、「絶対に行きたくない学校」から考えてみましょう。
「共学は嫌だ」「通学に1時間以上はかけたくない」「この制服は着たくない」など、ネガティブな条件で選択肢を削っていくと、意外と候補が絞られてきます。
3. 憧れの先輩の話を聞いてみる
身近にいる、志望校候補に通っている先輩がいれば、ぜひ話を聞いてみましょう。
パンフレットには載っていない学校のリアルな魅力や大変さを知ることで、志望度が固まったり、逆に「自分には合わないかも」と気づけたりする貴重な機会になります。
4. 少し背伸びした目標を設定してみる
今の学力では少し厳しいと感じる学校を、あえて目標に設定してみるのも一つの手です。
高い目標に向かって努力する過程で、学力は大きく伸びます。たとえその目標に届かなくても、結果的に当初の実力よりもはるかに高いレベルの学校に合格できる可能性が広がります。
第7章:知っておきたい!志望校を直前に変更するリスクとは?
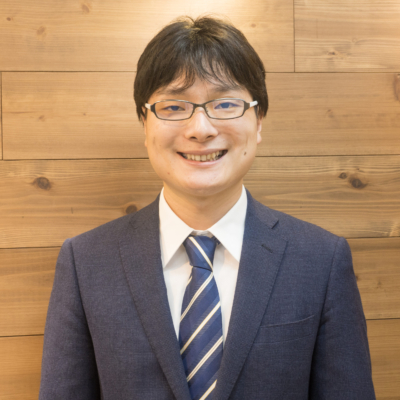
受験直前期になって志望校を変更することは、極力避けるべきです。それには明確なリスクが伴います。
- 学力面のデメリット: これまで対策してきた学校と出題傾向や科目が異なれば、十分な対策ができず、付け焼き刃の知識で本番に臨むことになります。特に過去問分析にかける時間が絶望的に不足します。
- メンタル面のデメリット: 「本当にこの選択で良かったのか」「前の志望校の方が良かったのでは」という迷いが、本番での集中力を著しく欠く原因となります。自信のないまま受験すれば、本来の実力を発揮することは困難です。
- 手続き面のデメリット: 出願書類の準備や、受験料の振り込みなど、直前の変更は手続き上のミスを誘発しやすくなります。
第8章:保護者の関わり方で合格が変わる!子供の志望校選びで親がすべきこと・してはいけないこと
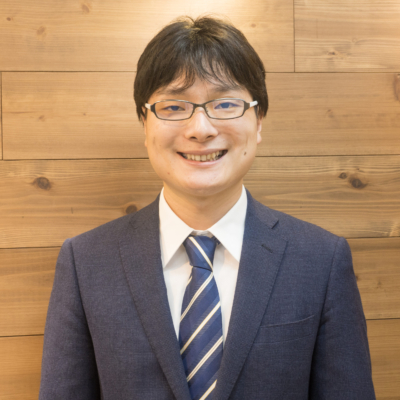
お子さんの志望校選びにおいて、保護者のサポートは不可欠です。
しかし、その関わり方を一歩間違えると、子どものやる気を削いだり、親子関係を悪化させたりする原因にもなりかねません。
【保護者がすべきこと】
- 情報収集のサポート: 学校説明会の日程調整や申し込み、資料請求など、子ども一人では手が回らない部分をサポートする。
- 良き相談相手になる: 子どもの話を頭ごなしに否定せず、「どうしてその学校に行きたいの?」と理由をじっくり聞く傾聴の姿勢を持つ。
- 学校見学への同行: 子どもとは違う「大人の視点」で学校をチェックし、客観的なアドバイスをする。
- 経済的な見通しを話す: 学費や塾代など、現実的なお金の話を正直に伝え、家庭としてどこまでサポートできるかを共有する。
【保護者がしてはいけないこと】
- 親の価値観や学歴の押し付け: 「この学校に入れば安泰だから」といった親の願望を押し付けるのはNGです。
- 子どもの意見の否定: 「あなたの成績では無理」と可能性を最初から否定する言葉は、子どもの自己肯定感を大きく傷つけます。
- 他人との比較: 「〇〇ちゃんはもっと上の学校を目指しているのに」という比較は、百害あって一利なしです。
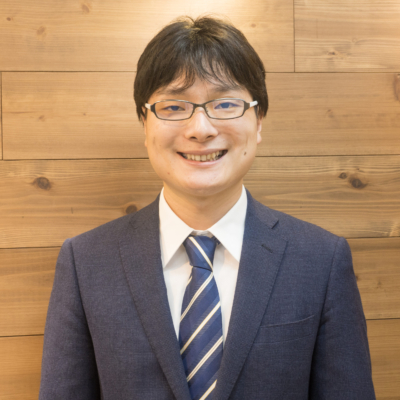
保護者の役割は、子どもに代わって進路を決めることではなく、子どもが自分自身で後悔のない決断を下せるように、環境を整え、選択肢を示し、最終的な決定を尊重して応援することです。
【まとめ】後悔のない選択のために、今日から始めよう
志望校を決めるべきタイミングは、受験の種類によって異なりますが、その根底にある原則は同じです。当然これよりも早く決めておくほうが、入試に対しては有利となります。第一志望を決めるリミットと捉えてもらえるとよいでしょう。
- 中学受験:小学5年生の冬まで
- 高校受験:中学3年生の夏休みまで
- 大学受験:高校2年生の冬~高校3年生の春まで
大切なのは「できるだけ早く大まかな方向性を決め、行動を開始すること」
そして、オープンキャンパスや模試を通じて情報をアップデートしながら、「必要に応じて柔軟に見直す勇気を持つこと」です。
志望校選びは、単なる受験のためだけの作業ではありません。自分自身の将来と向き合い、どんな環境で何を学び、どんな大人になりたいのかを考える自己分析のプロセスです。
まずはお子さんと「どんな学校が楽しそうかな?」と話してみることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、輝かしい未来へとつながっています。
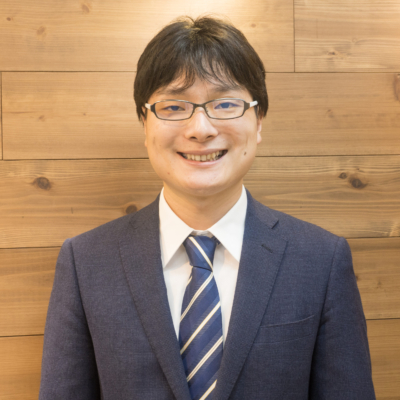
この記事が、皆さんの後悔のない進路選択の一助となれば幸いです。

この記事を読んでいる人には、こちらの記事もおすすめです!
https://kajikita-labo.com/kosodate/1290/





YouTubeでも情報発信をしています