ここ1・2年のニュースで、小学校のカラーテストでデジタルテストが導入されているというものがあります。
詳しくはYouTubeで、「小学校 テスト タブレット」と検索すると、九州の小学校での事例をニュース映像にしたものが見つかります。
映像を見ている感じ、まだまだ導入には程遠いなと感じています。
その理由が以下の3つなのですが、
- 指で書いていて、ものすごくやりにくそうだった
- 筆記用具を使わない
- テスト中に充電が切れている子がいて教室を歩いていた
という、算数や国語が得意になるか以前の問題が次々と起こっていました。

学校のテストがデジタル化されてしまうと学習の状況が分かりにくくならないか心配…
しかし、どういう力が働いているのか全国的にデジタル化の波はどんどんやってきています。カジきたラボのある京都でも、学校によっては導入する計画があるとか、ないとか…。
もちろん、働いている先生方の働き方改革は急務ですから、先生がもっと働けなどとは毛頭思っていません。ただ、導入されるデジタル教材の完成度が今ひとつだなぁっていうのが個人の感想です。
運用されはじめはきっと段取りがうまくいかず、成績の低下も場合によっては起こる場合があるかと思いますので、以下にやっておくことをお勧めしたい対策を列挙します。
今回は、「小学校テストデジタル化が始まったらやっておきたいこと」を特集します。
部分的に導入されているデジタルの学習教材と使っている生徒の様子を学習塾という現場で見ている一個人としての考えをまとめます。
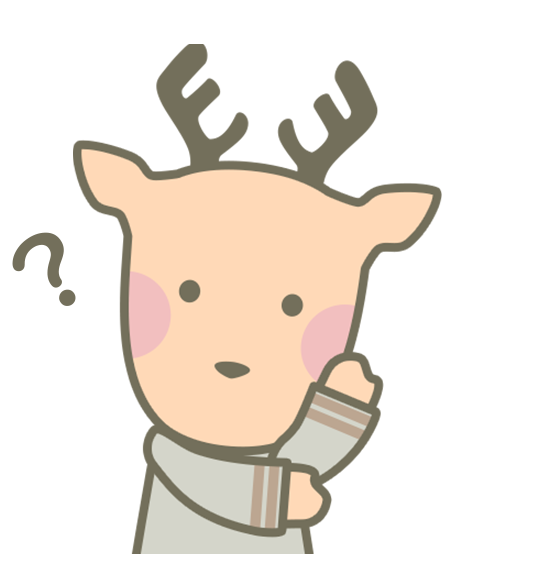
デジタルテストになったからといって勉強の仕方が変わるの?
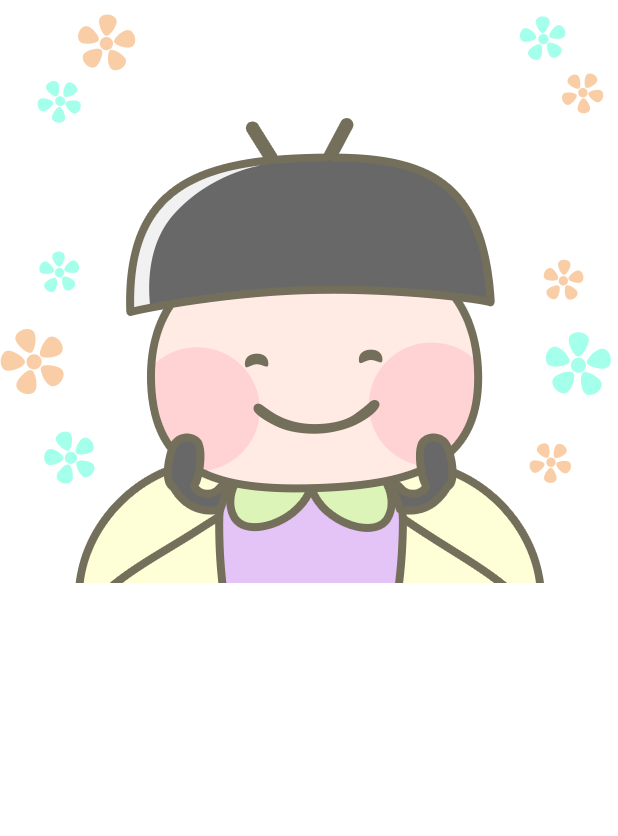
ペーパーテストでは考えてもみなかった違いが起こる場合があるんだ!
それでは、今回も学んでいきましょう!

テストの結果を親から見にいく
今までは、紙でテストを実施して、家に持って帰るスタイルだったので、親御さんも自然と目に入ることになりました。
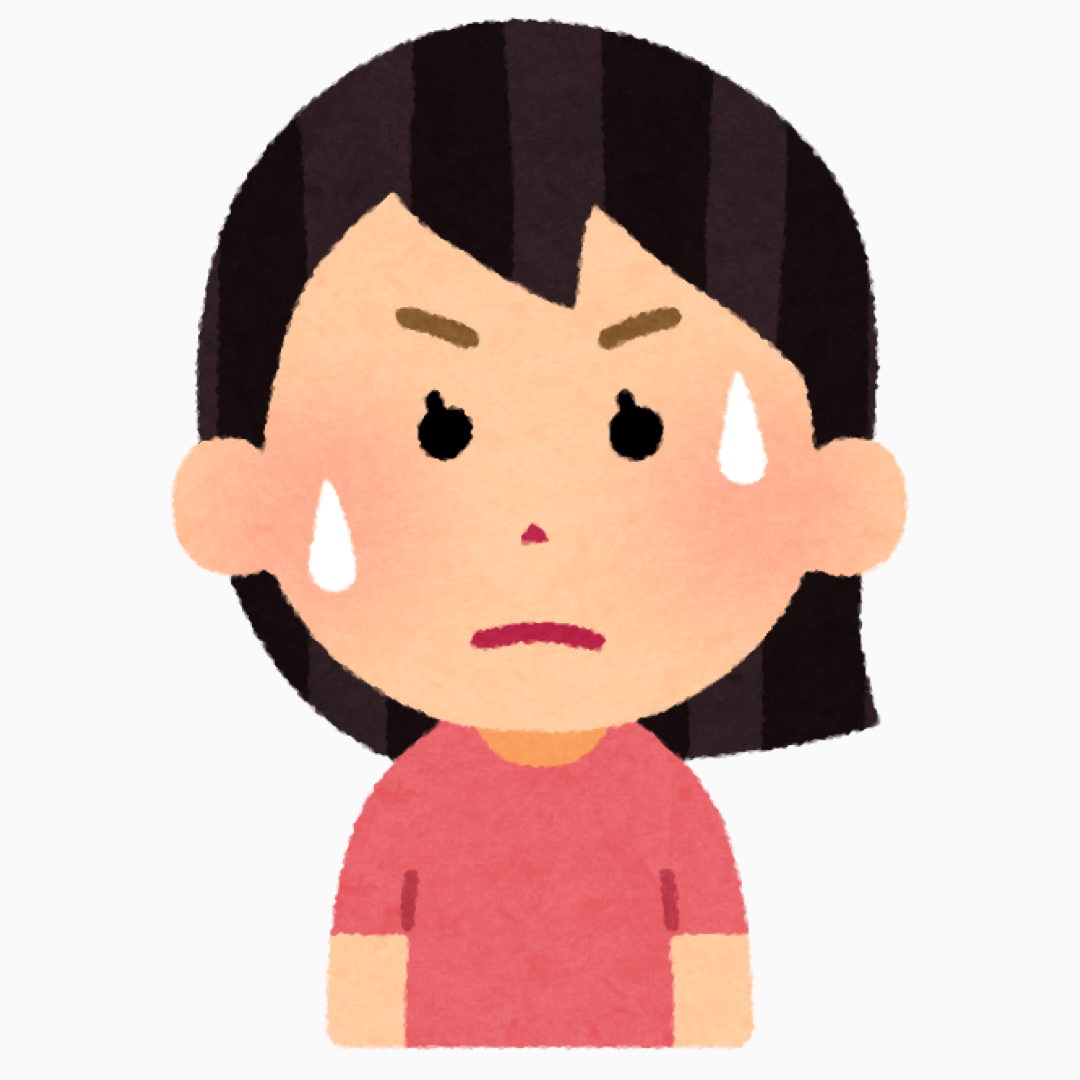
今でもテストやプリントを出さないけど…
一部のお子さんは、カバンの奥でシワクチャになってしまっていることもありますが、形や時期はどうあれ見ることができました。
しかし、デジタルテストではテスト結果は基本アプリで保護者の方へ配信となるようです。
つまり、これからテストをきちんと見るかどうかは、お子さんがテストを見せてくれるかではなく、親御さんが自身のスマホでテスト結果の配信を見逃さないかどうかにかかってくるという訳です。
ですから、これまで以上に親御さんがテスト結果を見ることに意識を置いていないといけないことになります。
一部の小学校では、テスト結果をプリントアウトして渡す対策をされているところもあるようです。
鉛筆とノートで家庭学習をする
デジタルでテストが実施されるようになると、普段の学習も全てタブレットでやりたくなる子が出てきます。
結論から言うと、タブレットをいままでのノートの代わりに活用した自学自習は、学習効率が低下し、成績の上昇が控えめになってしまう傾向があります。さまざまな研究機関の調査結果でも、タブレット学習は紙とノートを使用した学習に比べてテストの点数が低くなるとされています。
では、どこで差がつくのでしょうか
北欧スウェーデンの一部の市ではタブレットを活用した授業を廃止したところもあるほどです。
途中計算のしやすさ
途中計算のしやすさでは、圧倒的にアナログに軍配が上がります。細かな字を書けることはもちろん、大きな紙を用意すれば広いキャンバスに大量の数式を書くことができます。
一方でタブレットの画面は通常使われているサイズがおおよそ11インチ。これは、B5サイズ程度であり、学校などで特使われるノート見開きの半分ほどです。
拡大や縮小を活用することで、擬似的に無限大のキャンバスを手にいれることができますが、画面外に出てしまった領域は一目で見ることができないので学習効率という点では下がることが否めません。
振り返りのしやすさ
振り返りのしやすさもアナログが圧勝でしょう。アナログは一目で一覧できる情報量が多いほか、ページを高速で捲ることができます。
デジタルは物理的な大きさが存在していないため、意識して探しにいかないと見ることができないほか、高速でスクロールをすると、途中の内容は視認できません。
大きなキャンバスにたくさんの情報を書いたとしても、画面解像度の問題で、縮小しきった状態ではやはり内容を視認することは難しいでしょう。
まとめ
今回は、学校でのデジタルテスト導入が進んだ時に、ご家庭で気をつけていただきたいことを特集しました。デジタルは持ち運びが楽であったり、電車の中など空間が限定されている場合など便利なこともありますが、自学自習してテストの点数アップや成績アップを狙うためにはあまり向いていないというのが現状です。
ただ、運用の問題や、アプリの問題は次第に解決していくはずなので、デジタル化の波は変えられないでしょう。
アナログであれデジタルであれ、学習内容には差はありません。まずは、参考書とノートを使ったアナログの勉強で進めていくことが、少なくともここ10年は安全なのではないかと思います。
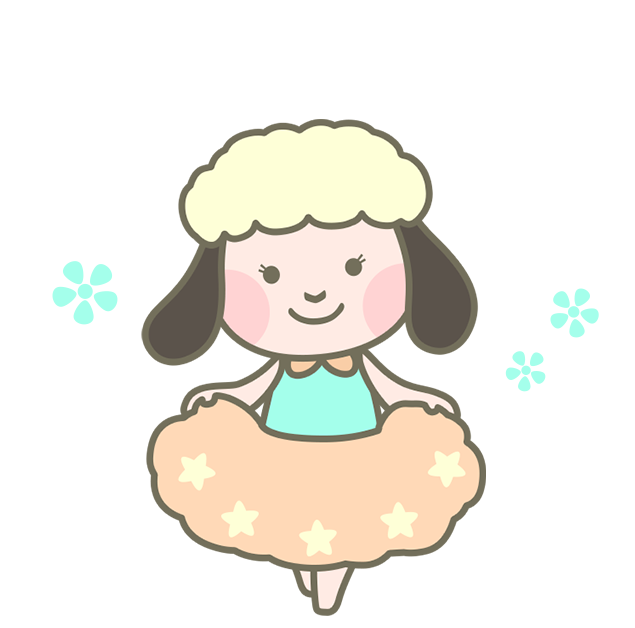
紙とペンを使うことが、この世からなくなる日は来るのかな?
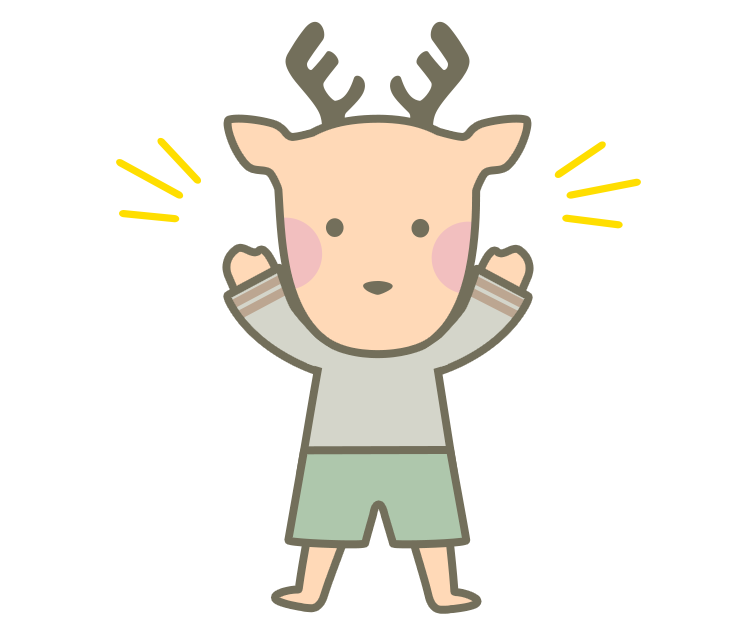
少なくとも今の赤ちゃんが成人する頃までは残るんじゃないかなぁ?

この記事を読んでいる人には、こちらの記事もおすすめです!
https://kajikita-labo.com/kosodate/1290/




YouTubeでも情報発信をしています